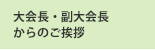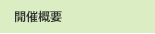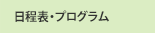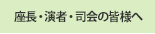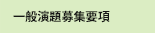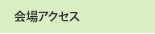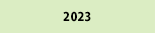“人間の尊厳”に関する石谷邦彦理事長からのメッセージ第2章 「人間の尊厳(human dignity)」と「生命の尊厳(sanctity of life)」
「生命の尊厳」は「人間の尊厳」と同じような文脈で語られるのであろうか?
今から30年以上も前、私の友人であり患者でもあった宗教哲学者 大出哲氏から、彼が中心となって翻訳したジョヴァンニ・ピコ・デッラ・ミランドラの著書“人間の尊厳について”を寄贈された。1496年の著書である。ピコは善きキリスト教徒として生き哲学と神学の研究家であったという。人間を卓越した存在と捉え、その一節に“神のアダムへの言葉−人間は自由意思に基づいて自己の本性を決定する”とあり私はかなり混乱した覚えがある。大出哲氏らは高名な哲学者 北海道大学名誉教授 花田圭介氏の愛弟子達である。
当時、私は「人間の尊厳」に帰するQuality of Life(QOL)概念を、1988年、日本の医学界に初めて紹介している。その際一般的に対極の概念として信じられていたSanctity of Life(SOL)についても大きな関心を持っていた。その後、約半世紀を経て、簡素化して図式的に言えば、SOL概念は延命医療の根拠であり、QOL概念は限りある人生の象徴であった。そしてそれらは調和を図りながらも、医療の上では先進国を中心としてQOL概念が大きな価値基準となっていった。すなわちそれはフーコーの言うエピステーメ(一時代の文化全体の規定にある認識の系、あるいは根底的な「知」)として理解される。
カントに始まる「人間の尊厳」概念は、20世紀には二つの世界大戦を経た巨大なカタストロフィに対峙しそれを克服する対抗理念として重要視され、国連憲章や世界人権宣言などにおいて「人間の尊厳と人権との相互関係」に明示された。20世紀後半から現在は、医療科学技術の発達に伴い「人間の尊厳」概念は生命倫理学的コンテクストの中で批判的反省を踏まえて激しく議論されている。それは緩和ケアの領域においてもゲノム医療、安楽死問題を含めて然りである。
カント的尊厳概念は、個人の自由とそれを律する事に対する無条件の尊重という考え方に基づいている。すなわち「自律」こそが尊厳の要諦なのである。
「人間の尊厳」という言葉には尊厳の尊重が含まれているが、尊厳の尊重が人間の生命に対する無条件の尊重に値するという結論には至らない。例えば安楽死を望む人の意思と実行に移すことを尊重する考えに賛否があることや、新型コロナウイルス・パンデミックでのトリアージについての倫理的議論などは良く知られている。その際引き合いに出される概念がSOL概念である。
20世紀の人道主義者と知られている密林の聖者 シュヴァイツァーの著書「生命への畏敬、Reverence of Life」の概念は“生命は、それ自体が唯一の(内在的)価値である”を主軸とし現在のSOL概念の議論の起点となっている。彼はサルトルの近しい親戚でもあり、哲学の分野でも優れた業績を残している。「生命の尊厳」の尊重は、人間の生命それ自体が尊重の対象となるのではなく、人間から見て自然な発達を経て生きていると考えられる生あるものを含んだ、全ての生物が尊重の対象となる。従って「Sanctity of Life」は、むしろ語源的にも「生命の神聖性あるいは不可侵性」と解釈される。シュヴァイツァーの生命に対する畏怖は、「形而上学的な畏敬」概念ともいわれている。これは宗教的背景に演繹される根拠となる。
さらにシュヴァイツァーは、生命が悲惨な状況にあることを説いておきながら、その一方ではそのような生命が唯一の価値であるという矛盾を抱えているが、彼の概念が環境倫理学の原理と目されている。
「生命の尊厳」概念は保護主義的であり、さらに自然への尊重の倫理学は意図的に反人間中心主義でもある。このように幾多の議論を経ながら、これまでのところ「生命の尊厳」を支持する説得力のある根拠付けは見出されてはいない。
「人間の尊厳」に関し“尊厳に値する者には尊厳を”ともいわれるが、カントは「自己自身に対する義務は、ただちに他者に対する義務を要請する」としたように尊厳を有する者はそれを担保する内在的な性質を基盤としなければならない。それは基本的人権の内実を供給する全ての人間に備わる道徳的な源泉である。
日本に「人間の尊厳」を見事に体現した作家が居た。それは三島由紀夫である。
参考文献
- 人間の尊厳について(De hominis dignitate):ジョヴァンニ・ピコ・デッラ・ミランドラ(Giovanni Pico Della Mirandola)著、大出哲・阿部包・伊藤博明訳、1985, 国文社
- 進行・末期がん治療−Quality of Lifeについて:石谷邦彦・漆崎一朗、からだの科学、Vol.142, p99-104,1988、日本評論社
- 生命への畏敬(Reverence for Life)−アルベルト・シュヴァイツァー書簡集1905−1965:アルベルト・シュヴァイツァー(Albert・Schweitzer)著、ハンス・ワルター・ベール(Hans Walter・Bahr)編、会津伸・村松国隆訳、1993, 新教出版社
- Sanctity of Life and Human Dignity: Kurt Bayertz, Philosophy and Medicine, 1996, Springer Dordrecht https://doi.org/10.1007/978-94-009-1590-9
- The Leagal Revolution: From “Sanctity of Life” to “Quality of Life” and “Autonomy”: John Keown, J Contemp Health Law and Policy, 14,253-285, 1998
- 2023.1.19 新年を迎えて、理事長からのメッセージ
石谷 邦彦
The International Research Society of the SCPSC理事長
医療法人東札幌病院 理事長
Asian Editor, BMJ Supportive & Palliative Care
2023年6月1日